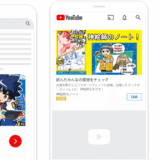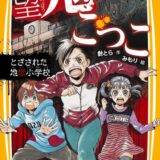マシュマロから創作相談をいただいたのだけど、回答が文字数上限を超過してしまったので、こちらで回答します!
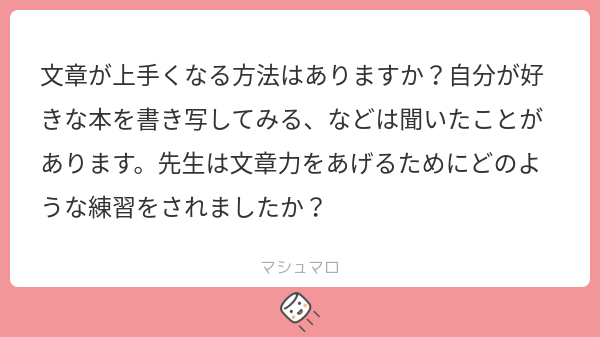
まず、文章の上手さとは…何か(ネットリ
…とかやりだそうかと思いましたが、論文みたいになっちゃいそうなので、まずはパッと思いついたことをテキトーに並べてみますね!
よく言われてるやつで、質問者さんもおっしゃってるやつですね!
僕も昔、宮部みゆき先生の短編を数本、写経したことがあります。
それが文章力の向上につながったかというと…。
正直、あんまり意味なかったな、というのが感想ですが…!
ただ、作家さんの呼吸みたいなものがなんとなくわかる気がするので、楽しいですよ。
僕は書くときも読むときも、口に出して音読まではしないけど、頭のなかでぜんぶ音にしているタイプです。
声に出して読んだときに、詰まらずにさらっと読める文章は、読みやすい文章かなと思います。(読みやすいと上手いはまた違うのかなぁ…)
しゃべりも抑揚が効いてないと、うまく意図や感情が伝わりづらいのと一緒で、文章もある程度の呼吸やリズムがないと、伝わりづらいかなと思ってます。
小説の文章を書くときは、接続詞をなるべく省くのは、やっているかなぁ。
接続詞って、文と文の論理関係を示すものなので、それがあるだけで読者を無意識に論理的にしてしまう――客観性を上げてしまうものかなと思っていて。
論文とかだったら全然OKなんだけど、小説の場合は、読者に、物語を客観的にではなく、主観的に捉えてストーリーに入ってもらいたくて書いているものなので、接続詞はなるべく削ります。
そもそもほとんどの接続詞って、わかりやすさの補助輪程度で、本来は必要ないものかと思っていて。
マンガのコマの中に、「つぎにこっちのコマを読む」みたいな注釈が入っていたらうるさいと思うんですけど、接続詞って似たようなところがあるかなと。
そんな注釈じゃなくて、流れのなかでそれをわからせるべきでは? と思うので、なるべく省くように意識してみると、文章うまくなるかなと。
「地獄への道は副詞で舗装されている」とスティーブン・キングも言ったそうな…。
安易に副詞を使っているときって、借り物のイメージでしか語れていない証拠なので注意しろよ、ってことかしらと思っています。
ただのパターン反応として文章を綴っている状態というか。
そういう文章は、ペラいよ、と。
まったく使ってはならない! ということではなくて、そうした「つい楽をしようとする人間の怠惰な脳への戒め」として、副詞が増殖したときは刈り取るように意識すると、文章うまくなるかなと。
……うーん。パッと思いつくのは、そんなところかしら。
ただ、このへんの話って、文芸をやってたときにはちょこちょこ話に出ていたんだけど、児童文庫でデビューしてからは、作家からも編集者からも聞いたことがないんですよね。
「わかりやすさ」の方向性は求められるけど、「上手さ」の方向性はほぼ求められてないというか。
僕もわかりやすさのためなら、副詞も使えば、擬音だって使っちゃいますし。
文芸の方にいたときは、文章で擬音なんか使えば100%注意されたと思うんですけど。
深みを優先するか、敷居の低さを優先するか、という方向性の違いではあり。
ということで、個人的には、「文章の上手さ」は、ベクトル値である、と思ってます。
“大きさ”だけではなくて、“方向”がある感じですね。上手い下手ではなく、どういう方向へ上手いのか。
そのへん、ジャンルや、作品によって変わってくるものなんだろうなと。
なので、一概にこういう練習をするといいよ、というのが言いにくいなぁというところはあるのですが。
大事なのは、「自分の描きたいものを、自分の伝えたい人に、過不足なく伝えられる」ことで、文章力はその手段なんだろうなと思います。
自分の描きたいものを描くためには、どういう方向性の文章力が必要なのか。
いろいろやってると、見えてくるものなのかもしれません。
がんばってください。